ADHDの治療薬 その効果は?
ADHDの特性を持つお子さんをお持ちの親御さんなら、一度はADHDの薬を飲めば学校の成績は上がるのではないかと期待したことはありませんか?私が感じたことですが、答えはNOです。NOと言えば語弊があるかもしれません。正しくは〝服用🟰成績が上がる〟ということが、NOです。ADHDの症状を抑えれば集中して勉強し、成績も上がると私も考えていました。しかし、そんな単純なことではなかったのが、経験して感じていることです。もちろん個人差が大きいと思いますが、娘の場合は成績に直結することはなかったと思います。ただし服用によって生活の困りごとが緩和され、勉強することができるようになり、結果、成績が上がったと感じています。
ADHDの治療薬とは
現在ADHDの治療薬には「コンサータ」「ストラテラ」「インチュニブ」「ビバンセ」の4種類があります。ADHDの中核症状である⚫︎不注意⚫︎多動性⚫︎衝動性を抑え、集中力の向上、ミスの減少を期待できます。また、その中核症状を和らげることにより二時障害の予防につながります。ただ効果には個人差があり、全ての人に薬の効果が期待できるわけではありません。医師と相談しながら適切な薬の種類と用量を見極める必要があります。治療薬と一口に言ってもADHDそのものを治す薬ではなく、薬を使ってADHDに由来する症状を抑え、症状によって起こっていた生きづらさを軽減することが目的になります。
ADHDの薬の種類と特徴
メチルフェニデート(コンサータ)
中枢神経刺激薬で、脳内のドーパミンの働きを高めることで、注意力を向上させてくれます。即効性が高く、1日1回の服用で効果が持続します。副作用に食欲不振や不眠があることがあります。
リスデキサンフェタミン(ビバンセ)
中枢神経刺激薬で、ドーパミンとノルアドレナリンの働きを活性化し、注意力を高めます。1日1回の服用で効果が続きますが、食欲不振や不眠などの副作用があります。
アトモキセチン(ストラテラ)
非中枢神経刺激薬で、脳内のノルアドレナリンを増やし、集中力や注意力を改善します。効果が現れるまで1ヶ月以上かかることがありますが、不安や抑うつ症状にも期待できます。
グアンファシン(インチュニブ)
非中枢神経刺激薬で、脳内の特定の受容体を刺激することで、衝動性や多動性を抑えます。感情の安定にも役立ちますが、初期に眠気や血圧低下を感じることがあります。
中でもコンサータとビバンセは、適正流通管理システムを通じて厳格に管理がされています。医師は専門医である必要があり、登録された医師しか処方することができません。また薬は、Eラーニングを受講し、合格した登録薬剤師がいる薬局のみ調剤することができます。服薬する患者も医師が登録する必要があります。この登録システムは、ADHD治療薬の適切な流通を確保し不正使用を防止する目的があります。患者情報の登録を義務化することで薬物依存や誤用のリスクを減らしています。
娘が服用している薬は
娘が現在服用しているのは「インチィニブ」「ストラテラ」の2種類です。飲み始めたきっかけは、高校3年生になったばかりの頃、全く勉強をしなくなっていた事と部屋が荒れ放題なのを見かねて、夫と相談し、心理検査をした病院へ薬を処方してもらえるよう相談に行きました。薬を服用すれば勉強をし、身の回りのこともできるようになるのでは?という期待からです。受診し処方をお願いしたところ「インチュニブ」が処方されました。
高校卒業後、大学生になり地元を離れて今まで通院していた病院へ通うことが物理的にできなくなったことと、一人暮らしにより精神的に不安定になったことから、現在住んでいるところから近いクリニックへ転院をしました。そこで新たに「ストラテラ」が追加で処方されました。
娘の薬の効果は?
初めてADHDの薬を処方してもらい、どうなったかというと・・・まず、飲みません。薬を処方してもらうことは、もちろん本人との話し合いのもとで行なったわけですが、娘自身は悩みは多かったものの、生活自体に困っているわけではなく、身の回りのことは私がしてくれているし、勉強についても大学に行くためにどうしたらいいか、という事も実感がなかったのでしょう。ADHDの特性のひとつである「先の見通しができない」という事と私の過度な先回りによって自分ごとととらえて行動する、ということができなくなっていたのだと思います。そもそも私たち親が「薬を飲めば娘の心配事がなくなるのでは」という、親の期待で薬を服用することにしたので、なかなか継続的な服用ができずにいました。
インチュニブは通常1〜2週間で効果が現れると言われています。毎日継続して服用が基本で、飲んだり飲まなかったり、断続的に服用すると効果が期待できなかったり副作用が出たりするリスクがあります。ですので、何とか毎日飲ませようと「飲んだ?」と確認するのですが、親にやらされていると感じて、ますます服用したがらなくなりました。「飲んでどう?」と聞いても「わからない」と怪訝そうに答え、聞かれるのも嫌がりました。服用したからといって、すぐに効果が現れる薬ではない為、娘も薬の必要性を感じていなかったと思います。そんな状況で、継続して服用する習慣をつけることができないまま、気がついたら飲む、という服用を続けていました。
インチュニブを服用して3ヶ月。1ヶ月分処方してもらったのがなくなるまで3ヶ月はかかりました。当然効果は全くと言っていいほど感じず、相変わらず勉強をする気配はなく、部活もやめ、部屋は床が見えないほどの汚部屋で、学校はかろうじて行っていたものの、1日中スマホを見ている毎日が続きました。それでも飲んでいればそのうち・・・などと淡い期待で、薬の服用を続けていました。医師に毎日継続して服用することが困難なことも相談しましたが、服用できるようになるまでには至りませんでした。
私は服薬が無意味に感じて、娘が大学に進学する機会に、インチュニブの服用を医師に相談してやめようかと娘に聞いたところ、あんなに積極的ではなかったにも関わらず、娘は続けると言いました。正直、娘はやめると言うと思っていたので意外な返事に驚きました。私には何も変わらないと言っていましたが、彼女の中では少なからず効果を感じていたのでしょうか。
大学生になり、一人暮らしになったことで、薬の管理は完全に娘任せになりました。時々「薬まだある?」と確認はしていましたが、自分からそろそろなくなるから受診しなくては、と言ってくることはありませんでした。それでも帰省する時は必ずインチュニブを持って帰ってきました。処方してもらった日数と受診の間隔があまり大きく乖離することがなくなってきました。新しく処方してもらったストラテラも、忘れる日はあってもほぼ毎日服用しているようでした。受診を忘れて薬がなくなった時も「これを飲まないと調子が悪くなる」と言っていました。
一人暮らしによって、生活面の困りごとが増え、自ら薬の力を借りようと考えたのだと思います。そこまで行き詰まって、やっと自分から服薬するようになりました。どんな病気でも、本人が病気と向き合い、治そう、良くなろう、なりたい、と思わなければ、いくら医療の環境が整っていても、家族が全力でサポートしても、良い方向にはいかないと言われますが、ADHDの症状を改善するのもやはり、本人が自分と向き合い症状を軽減したいと言う気持ちが第一なんだと強く感じました。
薬によってADHDの症状がどれだけ抑えられているのかは、血液検査や生体検査で測ることができないので、服薬🟰改善 とは言い切れないものがありますが、娘の場合をみてみると少しづつ改善しているように思います。例えば課題提出や予定を自分で把握することができるようになってきました。大学入学当初、つまり薬を毎日服用していない時は、課題自体を把握できていないことも多く、提出期限の1時間前にパニックになり電話をかけてくることが度々ありました。しかし現在はそういった電話はほとんどありません。期限内に提出することが難しい時は、自分から先生に連絡をしているようです。また、資料を無くしたり、PCをどこかに置き忘れて「どうしよう!!」という電話も度々ありました。今では全くなくなりました。肝心の成績は・・・というと、入学当初平均以下だったのが今は平均以上になりました。一概に薬の効果だけで改善されたのではなく、本人の意識だったり、先生のサポート、家族の対応、大学生活の慣れなど、様々な要因はあると思いますが、飲んでいる方が忘れることが少ないと本人も言っているので、間違いなく効果はあると思います。
ADHD治療薬を考えている人へ
私が娘のADHDを疑いながら、受診に至らなかった最大の理由として「娘にADHDの薬を飲ませたくない」ということがありました。ADHDの治療薬の中の「コンサータ」は、治療薬の中でも広く知られており、発達障がいのお子さんがいる親御さんは一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。中枢神経刺激薬であるため、長期使用や過剰摂取で依存や耐性が生じる可能性があり、副作用として不眠、不安などがあります。また食欲不振で食べられなくなってしまったり、薬が切れると疲れてぐったりする、というようなことも聞いたことがあります。私はこの一部の情報だけで、そんな怖い薬を娘に飲ませたくない。受診をしたらコンサータを飲まなくてはいけないんじゃないか。
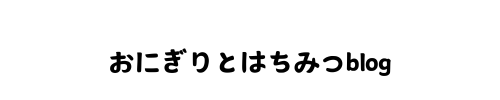


コメント