ADHDの子どもへの親の対応【これをすれば確実に成長できる】
わが子がADHD ではないかと疑い、全力でサポートを決意する私。ADHD は不注意などによって日常生活に困難をきたし、それによって傷つき、心理的不調で二次障害を引き起こす可能性が非常に高いと言われています。傷つく娘の姿は見たくありません。笑顔で楽しく生きてほしい。私の願いはただそれだけでした。
親の私がしてきたサポート
小さい頃から整理整頓ができなくて、無くしもの、忘れ物が多かった娘。私は娘が学校で忘れ物をして困ったり、先生に叱られたり、同級生にバカにされたりしないように、その日の学校の予定を把握。時間割や持ち物をチェックし、着るものも準備して身だしなみを整えてあげ、時間に遅れないように送り出していました。それは幼稚園〜中学生、高校生まで続いたのです。
高校の宿泊を伴う課外授業でも、私が荷物を準備し、荷造りをして送り出していました。ですので度々娘から「洗面用具はどこに入ってる?」「替えのハンカチはどこ?ウエットティッシュは?」とLINEで連絡が入ります。その度に「バッグ内ポケットの右側!あった?」と返します。
洋服も今のトレンドを私がチェックし、娘に相談もせず購入し着せていました。子供というものは見た目で判断するところが大きいと感じていたからです。同級生にバカにされないように、逆に可愛くて友達になりたいと思ってもらえるように。
娘の生き辛さを最大限に排除し、私が娘の人生を守る!と使命感でいっぱいでした。
そんな私の願いとは逆に、中学校では浮いた存在で辛い毎日を送っていました。学校での娘をサポートすることはできません。勉強ができたり、得意なことがあれば自信につながり、それが態度に現れ友達ができるのでは?と思い、学習塾、英会話、ピアノ、ダンス、スイミング、色々な習い事をさせました。それのどれもがそこそこ上手で、この子には才能がある。もっと力を伸ばしてバカにされないようにしなければ・・・私は更に使命感に燃えていました。
しかし、一定まで上達するものの飛び抜けることはなく、娘は次第にやめたがり、どれも中途半端なかたちでやめていきました。その度に私は、もっと頑張れば特別になれるのにもったいない・・・と落胆していました。
【野口心理カウンセラー野口嘉則さん】の動画に出会って
その日は、娘のことでひどく落ち込んだことがありました。何か参考になる動画はないかとYouTubeであれこれ検索していました。そのうち「【子育て】これだけは知っておきたい3つのこと」というタイトルの動画にたどり着きました。野口嘉則さんという心理カウンセラーで作家の方が発信しているチャンネルでした。この動画を視聴したとき、ものすごく衝撃を受けました。それはまさに私、夫が今までしてきたことがぴったり当てはまったからです。以下野口先生のお話です。
過保護や過干渉にならないように育てる
野口先生が「日本の親は過保護な傾向が強いんだな」と感じたエピソードが紹介されています。
ホームステイで外国人の若者を受け入れる活動をしていたとき、外国人に「日本はどう?」とよく聞いたそうです。すると「日本人は親切で大好きです」とか「日本はとってもいい国でますます好きになりました」とか本音で日本をほめてくれることが多かったそうです。
そこで野口先生はあえて「不満があるとしたらどんなことがある?」と聞いてみると、多くの場合に共通して返ってきた言葉が「子ども扱いされること」だったそうです。
例えば、寝る前にホームステイ先の家族に「明日は9時に出るので8時半にごはんを用意してくれるとありがたいです」と伝えて寝ます。10代、20代の若い子たちはギリギリまで寝ていたいわけです。ですので8時半にアラームをセットして寝ているのに、8時を過ぎたあたりから「そろそろ起きなくて大丈夫?」「もう8時過ぎてるよ」とホームステイ先の家族が言いにくることがよくあったそうなのです。
さらに「今日の降水確率は50%よ。傘を持っていきなさいよ」といった具合にまるで小さな子どもに言うようなことを言ってくるケースも珍しくなかったそうです。
こういった過保護な親のことを「ヘリコプターペアレント」とか「カーリングペアレント」というそうです。
「ヘリコプターペアレント」とは、上空を旋回するヘリコプターのように、子どものことに目を行き届かせている親のことだそうです。子どもが嫌な思いをしそうになったり、傷つきそうになったり、失敗しそうな状況になると、すぐさま急降下して救助しようとします。
「カーリングペアレント」とは、過保護な親をウィンタースポーツのカーリングに例えたものです。ストーンが進んでいく先の氷をブラシで掃いて、ストーンを誘導するカーリングのように、子どもの行く先々の障害物を先回りして取り除こうとする親のことだそうです。
このような過保護な親のもとでは、子どもは失敗や挫折をなかなか経験できません。人は悩みや失敗や挫折を経験しながら成長します。その機会を奪われてしまった子どもは心理的に自立できなくなってしまうと野口先生は続けました。
さらに、子どもというのは、親から受容されるという経験をたくさんすればするほど、自分で自分を受容できるようになるそうです。
例えば、小学校高学年の子どもが、朝、学校に行こうとしています。
すると母親がやってきて
「今日の4時間目は、音楽の授業が体育に変わったんでしょ。体操着は持ったの?」
「今日の降水確率は50%だって。傘を持ったほうがいいわよ」
この母親は、子どもが十分に自分で考えてやれることを代わりにやってしまっています。つまり、失敗を体験する機会を子どもから奪っているのです。
そして、「子どもが傷つかないように、子どもが失敗しないように」と先回りする親の行為は、実は・・・
「そのままのあなたでは受容できませんよ」というメッセージとして子どものこころに届いてしまっているんです。
私はこれを聞いた時、「まさに私のことだ・・・」と衝撃がはしりました。娘を友達からバカにされないように着飾り、時間割や持ち物を把握し準備して持たせ、娘が失敗して傷つかないように常に先回りをして手や口を出してきました。忘れ物や失敗が多いADHDの娘が、自信を無くし、二次障がいにならないようにと常に先周りをして生きにくさを排除しようと必死でした。
子どものサポートをしているつもりが、結果的に
「傷つくあなたは見ていられない」
「嫌な思いをするあなたは受け入れられない」
「失敗するあなたは受容できない」
というメッセージになって子どものこころに届いてしまっているそうです。
そうすると子どもは、自分が傷つくことやネガティブな感情を感じること、失敗することを受け入れられなくなり、それらを過剰に避けるようになるそうです。
つまり、「自己受容」ができず、自己肯定感がなかなか育まれない状態になってしまうそうです。
私は、自己肯定感が下がらないようにと、失敗しないよう先回り先回りして行ってきた行為が、実は娘の自己肯定感をどんどん下げていく行為だったのです。
まさに野口先生のおっしゃる通りでした。
娘は自己肯定感が低く、ダメな自分、実行できない自分、自分を責め、理想の自分とかけ離れていることに悩み苦しみ続けました。理想の自分とは、今考えると私(母親)が考える理想の娘だったのです。
さらに野口先生は「過干渉」についても触れています。
子どもに対して「あれをしなさい」「これをしなさい」「それはやめておきなさい」とやたらと口出しをするのが過干渉です。
子どもは育つ過程で、自分と他者との間にしっかり境界線を引くことによって、自分のこころの中に安全領域を作るそうです。「ここから内側は誰からも干渉されない」という安全領域を作り出すことで、自分が自分であることの確かさを築き上げていくそうです。その境界性は、親との間に引いていくことがとても大事なんだそうです。親が干渉するということは、親が子どもの境界線を乗り越えて子どもの人生に侵入していることになるそうです。
そうすると子どもは境界線を引けないので、心理的に自立できなくなってしまうといわけです。
干渉には「あれしなさい」「あれはやめなさい」という直接的な干渉ばかりではなく、親が嫌だと思っているような選択を子どもがしたり、親の助言を子どもが採用しなかったときに「親がため息をつく」「悲しい表情になる」「不機嫌になる」といった方法で、親が間接的に子どもに干渉し子どもをコントロールするといったこともよくあるそうです。
言葉では「あなたの好きなようにしたら」と言いながら、表情は悲しい顔をしたり不機嫌な表情をするパターンです。言っていることと表情が矛盾しているわけです。この2つの矛盾が発せられている状況を、ダブルバインド(二重拘束)というそうです。このダブルバインドの状況に長時間置かれると精神の不調に陥りやすいそうです。
はっとしました。ここまで全て娘にしてきた接し方だったからです。
髪型、服装、持ち物、娘の好みは聞かず、私好みで揃え、習い事は「やってみたい?」と聞くことはしましたが、本人がやりたいと言うまで「やったらこんな良いことがあるよ」と誘導し、進路も「この学校へ行けば友達も新しくできるし、勉強ができれば選択肢もひろがるよ」と中学受験を勧め、高校で勉強につまずけば「勉強なんてできなくたって活躍している人はたくさんいるよ」と言いながらも少しでも偏差値の高い大学に進学させようと塾や家庭教師をたのんだり・・・部活も嫌ならやめたら?と言っておきながら、やめたいと言い出した時は絶対やめたらだめと怒ったり・・・
娘との境界線を乗り越えて、娘の人生にどっぷりつかり、娘の人生を私が歩いていました。
ADHDでも立派にして不自由なく社会で暮らしていけるように・・・私がそうしてみせる、と親としての責務だと思っていました。こんなにサポートしてきたのに、どうして娘は自己肯定感が低く、自分を責め、死にたいなんて言うのか、ADHDという疾患はどんなに支えても、こころを支えることはできないんじゃないのか・・・と途方にくれていたのです。
それが、この動画を視聴して、ADHDが娘を追い詰めていたのではなく、私と夫が彼女を追い詰めていたのだ・・・と気付かされたのです。
しかし、私は同時に「この話しは理解した。私の考えや接し方が問題だったのはわかった。でも・・・」という思いがこみ上げてきました。
そうです。娘はADHDなのです。定型発達のお子さんなら過保護や過干渉をやめることはできても、娘はサポートしなければ、たちまち失敗を重ね、生活は破綻し自己嫌悪に陥るでしょう。それができないから困っているのよ・・・と肩を落としていました。つづきを聞くまでは・・・
子どもの生きるチカラを信じる
野口先生は「子どもを信じることが、子どもへの最大のサポートになる」とおっしゃっています。
ここで「7つの習慣」という著書コヴィー博士の話を紹介しています。
コヴィー博士にはショーン君という息子がいました。ショーン君は学校の勉強が苦手でスポーツも苦手、友達ともうまくやれていませんでした。
そこでコヴィー博士と奥さんは、とにかくショーン君をサポートしようとして、いつも「おまえはやれば出来るやつだ」と前向きな言葉を投げかけたり、野球の練習相手もしました。野球の練習中に同級生がはやしたてるとその同級生のところに行き「今、練習中なんだ。邪魔はしないでくれるかい」と言ったり、できる限りのことをやっていました。ところが、まったくショーン君の状況は変わりませんでした。
壁にぶち当たったコヴィー博士は心理学を学び、とても大事なことを知ったのです。それは「自分が相手のことをどのように見ているかが相手に大きな影響を与える」ということです。
コヴィー博士は「自分たち夫婦は息子に対して『彼は劣っているから自分たちが助けてやる必要がある』という見かたをしていた」と気付くのです。
「ショーンは劣っている」という考えでショーン君に接していたので、サポートすればするほど、ますます彼を無力な存在にしていたのです。言葉ではポジティブな言葉を投げかけていたけど、ショーン君に伝わっていたのは「お前は不十分だ」「助けが必要な存在なんだ」というメッセージだったのです。
このことに気付いたコヴィー博士は「息子のチカラを信じて見守ろう」と決めました。ショーン君も最初は、これまで通りの過保護なかかわりを求め抵抗しましたが、「お前は十分にやっていけるよ」という態度を貫きました。その結果ショーン君の個性が開花し、活躍する大人になったそうです。
人は誰でも生きるチカラを持っています。肉眼に見える姿に惑わされず、心の目で子どもの生きるチカラの素晴らしさを見つめることで子どもが自分のチカラで生きていけるようになるというのです。
子どものチカラを信じるというのは、親の勝手な期待を押し付けるのとはまったく違うをいうことに注意が必要です。
「この子は必ずがんばり屋になって、勉強をがんばって、いい大学に入ってくれる。親としてそれを信じるぞ」というのは、親の勝手な期待をおしつけているだけなので、子どもにとっては負担になります。信じるというのは「勉強をがんばろうががんばるまいが、どんな選択をし、どんなプロセスを経ようがこの子はこの子の個性を発揮して、自分らしい幸せな人生を実現できる」「幸せな人生を実現するチカラを、この子は全て持っている」ということです。
私はずっと「ADHDのあなたは失敗するからお母さんが支えるよ」「ADHDのあなたはお母さんのいう通りにしないと周りから変に思われるよ」「ADHDなんだから何かひとつでも自信がつくことを身につけないと」「ADHDなんだから勉強ができないと周りから認められないよ」「ADHDなんだから・・・」そう考えながら娘をサポートしてきたのです。それは娘へメッセージとして伝わっていたのでしょう。
そして「娘はきっと、何か得意なことを見つけて、いい友達ができて、いい大学に入ってくれる」と期待していました。まさに期待をおしつけていたわけです。
この動画を視聴したのをきっかけに、私は娘への接し方を変え、娘の生きるチカラを信じる決心をしました。
そして今、娘は少しづつ自分のチカラで歩き出しています。
3つめが気になった方はぜひ野口先生の動画をご視聴ください。お子さんのことで悩んでいる方は、きっと変われるきっかけがつかめるはずです。
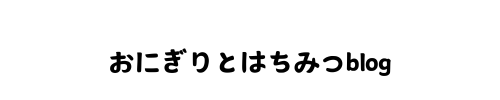



コメント